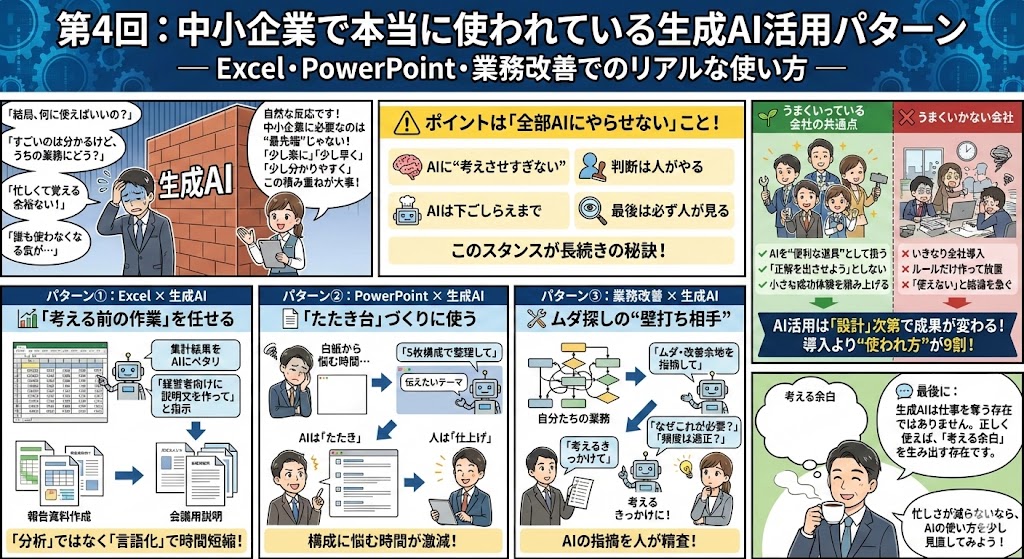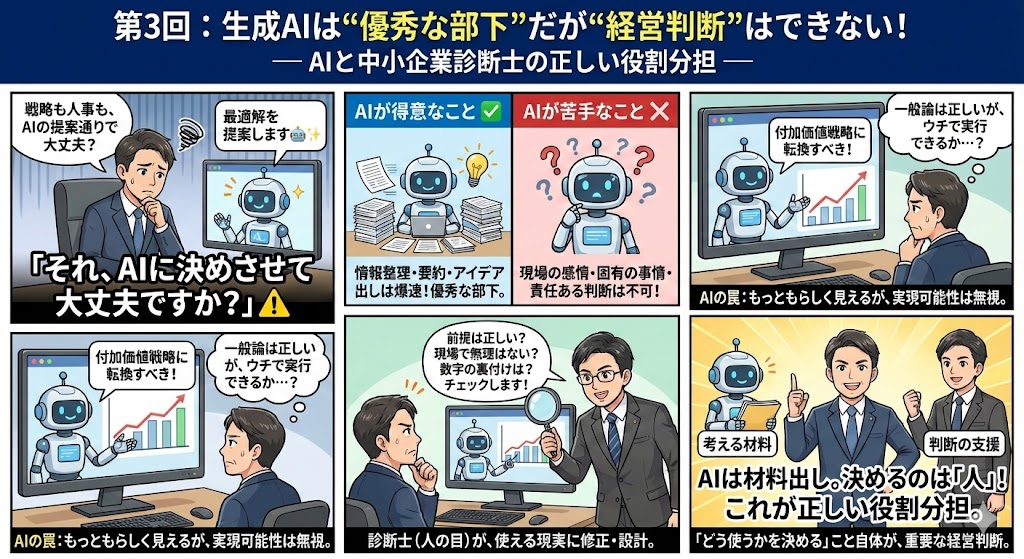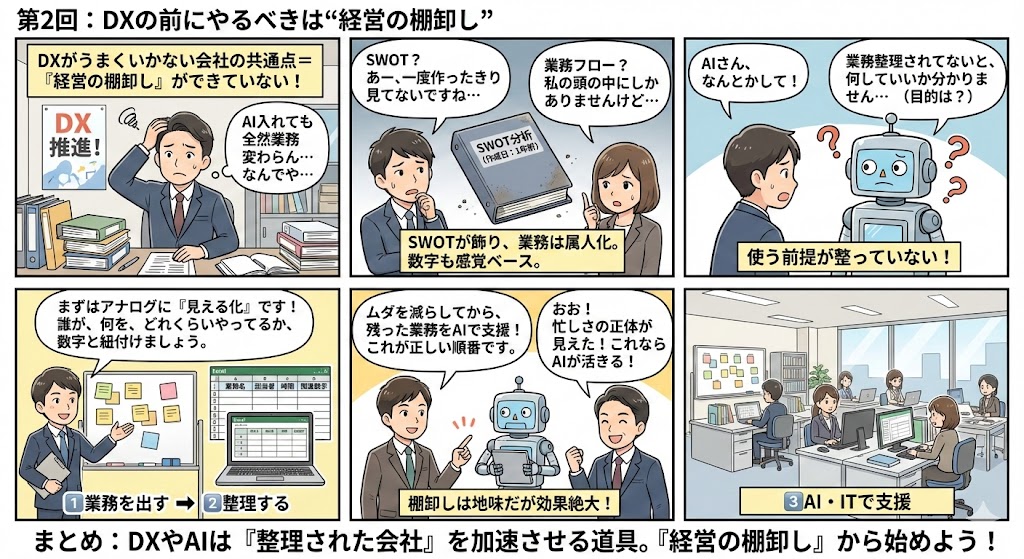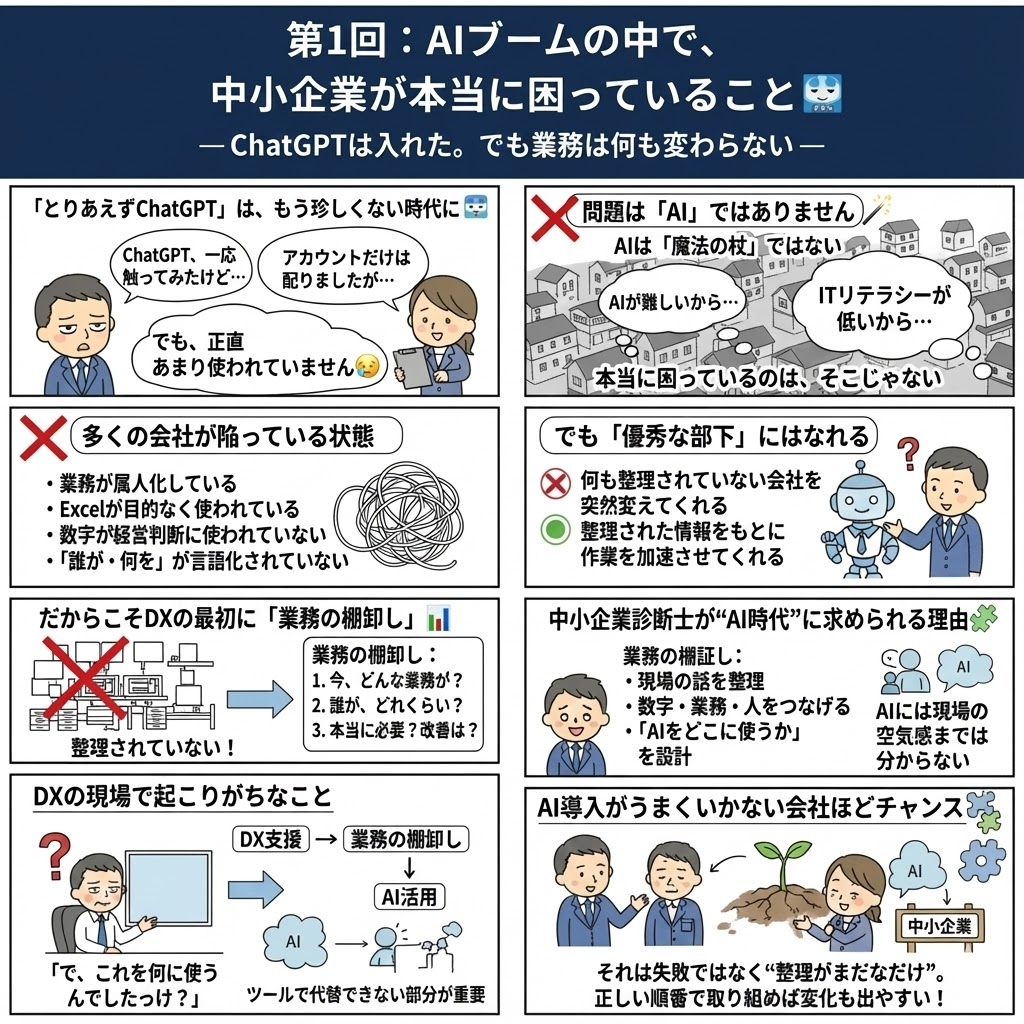2025.11.13
【Day4】チームで共有・定着させる仕組みをつくる〜個人のAI活用を“組織の成果”に変える〜
こんばんは。i-consulting office(アイ・コンサルティング・オフィス)の田中健太郎です。
私は「社長も社員も、働くことが楽しいと思える会社づくり」
をお手伝いすることを使命に、中小企業の経営支援を行っています。
そんな私の提供できるサービスを考えてこんな経営者に出会いたいと考えています。
- DX推進/生成AI活用を社内に取り入れたいが何から始めていいかわからない。
- 経営数字を使った根拠ある経営判断をしたい。
- 自社の強みを見直し、根拠のある経営計画を作成したい。
- 採用・定着を実現するための理念策定・浸透を行いたい。
といろいろ書いてますが、経営に関するお困りごとは気軽にご相談ください。
当社は「わかりやすく、具体的に」をモットーに、経営の現場ですぐに役立つ支援を心がけています!
本日は「Day4】チームで共有・定着させる仕組みをつくる〜個人のAI活用を“組織の成果”に変える〜」というタイトルで書いておきます。
なんだかんだ言っても、新しいモノ・コトはなかなか定着しないわけでして、しかもAIは絶対にしょっちゅう触る人とめったに触らない人では生産性や成果に差が出てしまうのではないかと思います。
🌟こんな方におすすめ
- 社員が個々にAIを使っているが、全体最適の効果が見えない
- チーム内でAI活用を広げたいが、定着の仕組みづくりができていない
- 経営層と現場の間でAI活用への温度差がある
🧭はじめに:AI活用は「個人技」から「組織文化」へ
Day1〜3で、
- AI導入の意義
- 業務の見える化
- 無料ツールを使ったスモールスタート
ここまでのステップを進めてきました。
しかし、会社としてAIの恩恵を最大化できるかどうかは「定着」にかかっています。
実際、多くの企業で起きているのが次の課題です。
- 一部の人だけがAIを使っている
- AIノウハウが属人化し、他部署に広がらない
- 「AIを試したけど続かなかった」
これは珍しいことではなく、多くの企業で共通する“AI導入の壁”です。
そこで本記事では、AI活用を組織文化として根づかせる方法を、正確な知識に基づきながら解説します。
🧩ステップ①:まず「成功体験」を社内で共有する
AI導入を定着させる最初のポイントは、成果を社内で見える化することです。
例として、以下のような共有テンプレートをおすすめします👇
| 活用事例 | 担当者 | 効果 | 使用ツール |
|---|---|---|---|
| 見積文の下書きをAIで作成 | 営業部 山田 | 1件あたり15分削減 | ChatGPT |
| 会議の議事録をAIで要約 | 管理部 佐藤 | 作業時間80%削減 | Notion AI |
| 広報チラシのたたき台をAIで作成 | 総務部 田中 | 外注コスト削減 | Canva |
👉 ここで重要なのは、ツール名よりも「成果」を強調すること。
「ChatGPTを使いました」よりも、
「作業時間を◯分短縮しました」
「外注費がゼロになりました」
といった成果の方が社内に響きます。
🧰ステップ②:「社内AIポリシー」を整備する
AIを組織で利用する場合、セキュリティ・個人情報保護・責任範囲のルールは必須です。
特に注意したい点は以下です:
- 外部AIサービス(ChatGPTなど)では、機密情報や個人情報を入力しないことが推奨されている
- 生成AIは誤回答(AI hallucination)をすることがあるため、必ず人が最終確認を行う必要がある
そこで、以下のような「AI利用ポリシー」を社内で文書化するのが有効です👇
📝社内AIポリシー(例)
- 顧客名・金額・個人情報など機密情報は原則入力禁止
- AIの出力内容は必ず最終確認者がチェックする
- 社外に出す文章は上長に確認を取ってから利用する
- 著作権・責任の最終的な所在は確認者にある
- 新規AIツールを導入する前に情報システム部門へ報告する
これらをTeamsや社内ポータルに掲示しておくことで、
安心してAIを利用できる環境づくりが進みます。
🧩ステップ③:「AI活用チャンネル」を作る
AI活用を習慣として根づかせるには、コミュニティづくりが効果的です。
以下のような仕組みが特におすすめです👇
1️⃣ Teams / Slack に「#AI活用チャンネル」を作る
- 「このプロンプト便利でした!」
- 「この資料はAIでどこまで作れる?」
など、気軽に投稿できる雰囲気が重要。
2️⃣ 月1回の「AI活用ミーティング」
- 1部署1事例を持ち寄るだけでOK
- 成功・失敗含めて共有すると改善が進む
3️⃣ 社内AIニュースレター
- 「今月のAIトピック」
- 「便利プロンプト紹介」
- 「活用事例ベスト3」
小さな取り組みの継続が、
**“AIを使うのが当たり前の組織文化”**をつくります。
🧠ステップ④:チーム単位での「AI推進リーダー」を任命する
全員が同じスピードでAIを使いこなすのは難しいため、
各部署に**AIアンバサダー(推進リーダー)**を置くと効果的です。
🏅AI推進リーダーの役割例
- 部署内のAI相談窓口
- 成功事例・便利プロンプトの収集と共有
- ミニ勉強会の企画
- 新ツールのテスト導入
現場主導の改善サイクルが回るため、AI活用が“本社指示”ではなく“自分たちの業務改善”として根づくというメリットがあります。
📈ステップ⑤:成果を“見える化”し、経営判断に活かす
AI活用が広がってきたら、次は効果測定です。
以下のような表で管理すると、経営会議での報告にも耐えうる資料になります👇
| 部署 | 活用ツール | 削減時間/月 | コスト削減額/月 | 効果レベル |
|---|---|---|---|---|
| 営業部 | ChatGPT | 15時間 | 約45,000円 | ★★★★☆ |
| 総務部 | Canva | 10時間 | 約30,000円 | ★★★☆☆ |
| 経理部 | Copilot | 5時間 | 約15,000円 | ★★★☆☆ |
👉 “時間削減”は「業務改善」、“コスト削減”は「経営効果」として伝えやすくなります。
💬AI導入を“組織文化”にするための3つのポイント
1️⃣ 小さな成功を積み重ねる
→「まずは1つの業務」でOK
2️⃣ チームで情報を共有する
→ Slack・Teams・定例会など
3️⃣ AI活用が評価される仕組みを作る
→ 業務改善報告書にAI項目を追加する
→ AI活用を人事評価の加点対象に
AIは「評価制度」とセットにすると一気に定着します。
🧭まとめ:AI導入は“個人”ではなく“チーム”で進化する
AI導入の本質は、ツールの導入ではなく組織の変化です。
- 個人の成功をチームに広げ
- チームの成果を会社の成長につなげる
これが、AI時代の組織づくりの新しい常識です。
まずは今日、
社内チャットに「AI活用チャンネル」を作ることから始めてみませんか?
🚀次回予告(Day5)
テーマ:成果を数値化!AI導入の効果測定と次のステップ
— “使って終わり”にしないための検証と改善の仕組みづくり —
✅サンプル① 社内AIポリシー(テンプレート)
以下は、中小企業でもすぐ使えるように実務レベルで整理したテンプレートです。
「そのまま社内文書化できる」レベルに整備しています。
【社内AI利用ポリシー(テンプレート)】
■1. 目的
本ポリシーは、生成AI(ChatGPT、Copilot 等)を安全かつ効果的に利用し、業務品質向上・生産性向上を図ることを目的とする。
■2. 適用範囲
本ポリシーは、当社の社員・アルバイト・派遣社員など、業務でAIツールを使用するすべての者に適用する。
■3. 基本方針
- AIは業務効率化のために積極的に活用する
- 機密情報・個人情報の保護を最優先とする
- AI出力は誤情報を含む可能性があるため、必ず人が最終確認を行う
- AI利用の透明性を確保し、安全に活用できる環境を整備する
■4. 利用ルール
【4-1. 入力してはいけない情報】
以下の情報は外部AIサービスへ入力禁止とする:
- 顧客名、個人名、住所、連絡先
- 契約金額、見積金額、取引条件
- 社内の機密情報(開発情報、財務情報、社内資料 など)
- 社外秘のデータ(顧客データベース等)
※Microsoft Copilot(企業向け)の場合、セキュリティ構造が異なるため、情報システム部が利用可否を判断する。
【4-2. 出力内容の取り扱い】
- AIが生成した文章・資料は、必ず人(最終確認者)が内容の正確性をチェックする
- 事実ベースの内容は必ず一次情報で裏取りする
- 著作権・責任は、最終確認者にあるものとする
【4-3. 公開手続き】
AIを使って作成した資料を社外に公開する場合:
- 上長の承認を得ること
- 二重チェック体制を推奨
【4-4. 新規AIツールの導入】
新しいAIツールを利用する場合:
- 情報システム部門に事前報告・承認を得る
- セキュリティ確認(データの扱い、学習有無等)を実施する
■5. 禁止事項
- 機密情報の入力
- 虚偽情報・著作権侵害を助長する利用
- AI出力を“鵜呑み”にしての利用
- 不適切なプロンプト入力(誹謗中傷、偏見を助長する内容 等)
■6. 推奨事項
- チーム内で成功事例・便利プロンプトを共有する
- AI活用チャンネル(Teams/Slack)へ積極投稿する
- AIスキル向上のための社内勉強会へ参加する
■7. 免責事項
AI出力には誤りが含まれる可能性があるため、利用者は必ず内容を確認し、会社は誤用による責任を負わないものとする。
■8. 改定
本ポリシーは、技術動向や法令の変更に応じて適宜改訂する。
✅サンプル② AI導入 効果測定フォーマット
管理部門・経営層がそのまま利用できる、Excel化を前提とした表形式です。
【AI活用 効果測定シート(テンプレート)】
■基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記入日 | yyyy/mm/dd |
| 部署名 | |
| 記入者 | |
| 利用したAIツール | ChatGPT / Copilot / Canva / Notion AI / その他 |
■1. 活用した業務
| 業務名 | 活用前の作業内容 | AI活用後の作業内容 |
|---|---|---|
| 例:見積書の文章作成 | 手作業で文章作成(30分) | AIで下書き作成後、微修正(10分) |
■2. 効果(定量評価)
| 項目 | Before | After | 削減量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 作業時間(1件) | 30分 | 10分 | 20分削減 | |
| 月間件数 | 30件 | 30件 | – | |
| 月間時間削減 | – | – | 600分(10時間) | |
| 時給換算 | – | – | 3,000円/時間 | 業務単価 |
| 月間削減額 | – | – | 30,000円 |
■3. 効果(定性評価)
| 評価項目 | 評価(◎/○/△) | コメント |
|---|---|---|
| 業務品質の向上 | ||
| 作業負荷の軽減 | ||
| スピードアップ | ||
| 顧客満足度の向上 | ||
| 属人化リスクの低減 |
■4. 総合評価
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総合効果(★1〜5) | ★★★★☆ |
| 今後の改善点 | |
| 継続利用の可否 | Yes / No |
■5. 経営層向けサマリー(自動生成欄)
- 月間削減時間:〇〇時間
- 月間削減額:〇〇円
- 特に効果の大きかった業務:
- 継続・展開すべきポイント:
お問い合わせ
本日は「【Day4】チームで共有・定着させる仕組みをつくる〜個人のAI活用を“組織の成果”に変える〜」というテーマのブログを書かせていただきました。中小企業様の生成AI導入の参考になれば幸いです。
本日はいろいろとサンプルも作成してみました。よろしければご利用ください。
i-consulting officeでは生成AI導入のための研修・導入支援を行っています。
ご興味・ご関心のある方はぜひお問い合わせください。
お問い合わせページ:https://icon-office.com/contact
Instagram:https://www.instagram.com/i_consulting_offic👈Instaフォローお願いします!
LINE公式アカウント:https://lin.ee/xHeD62c
宜しくお願いします!
本日のお仕事
本日は持続化補助金相談3連発!
・C社 美容業 エステサロンに関する補助金
・H社 建設業 カフェに関する補助金
・F社 就労支援事業 新製品開発
よくしゃべったけど、しゃべりすぎ。お客様にもっと話をしてもらおうと反省