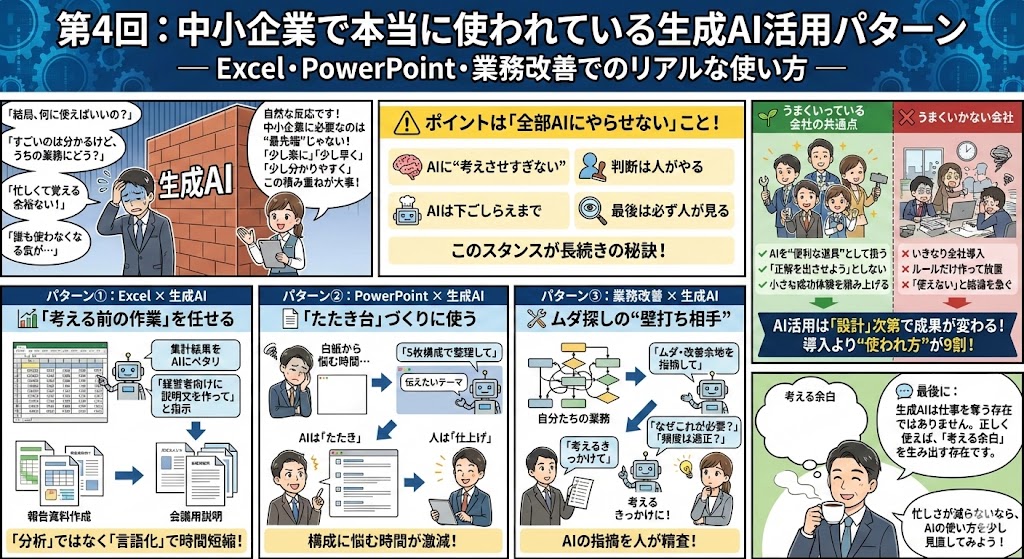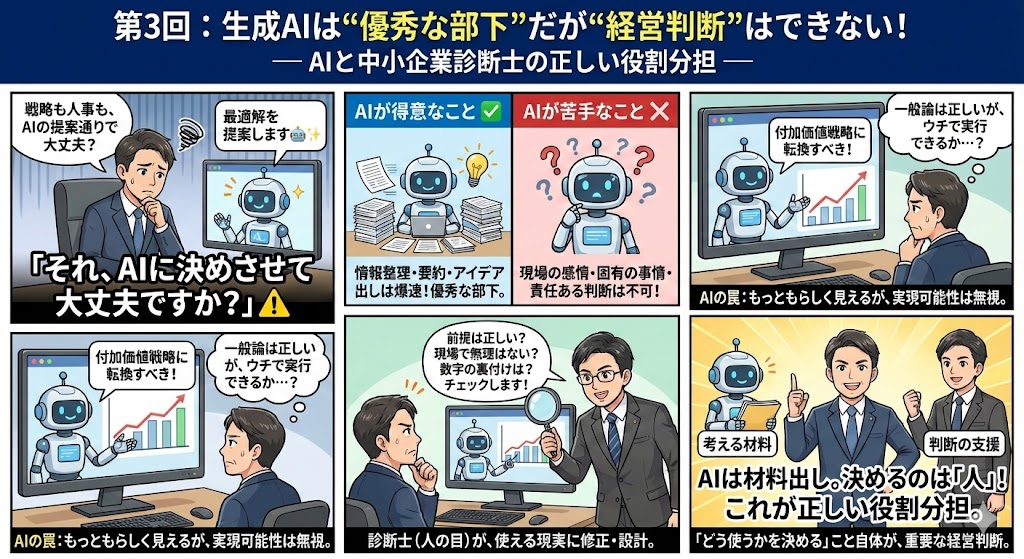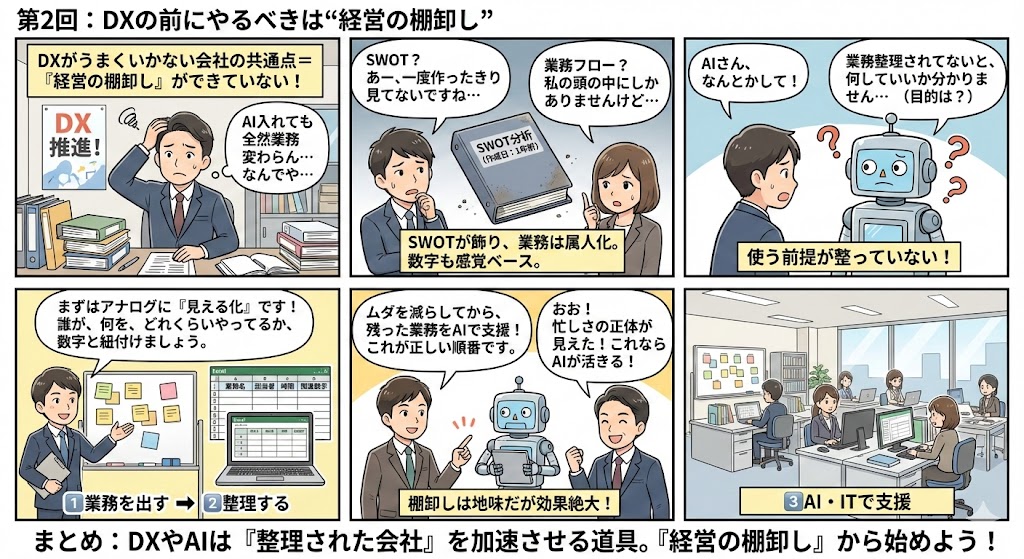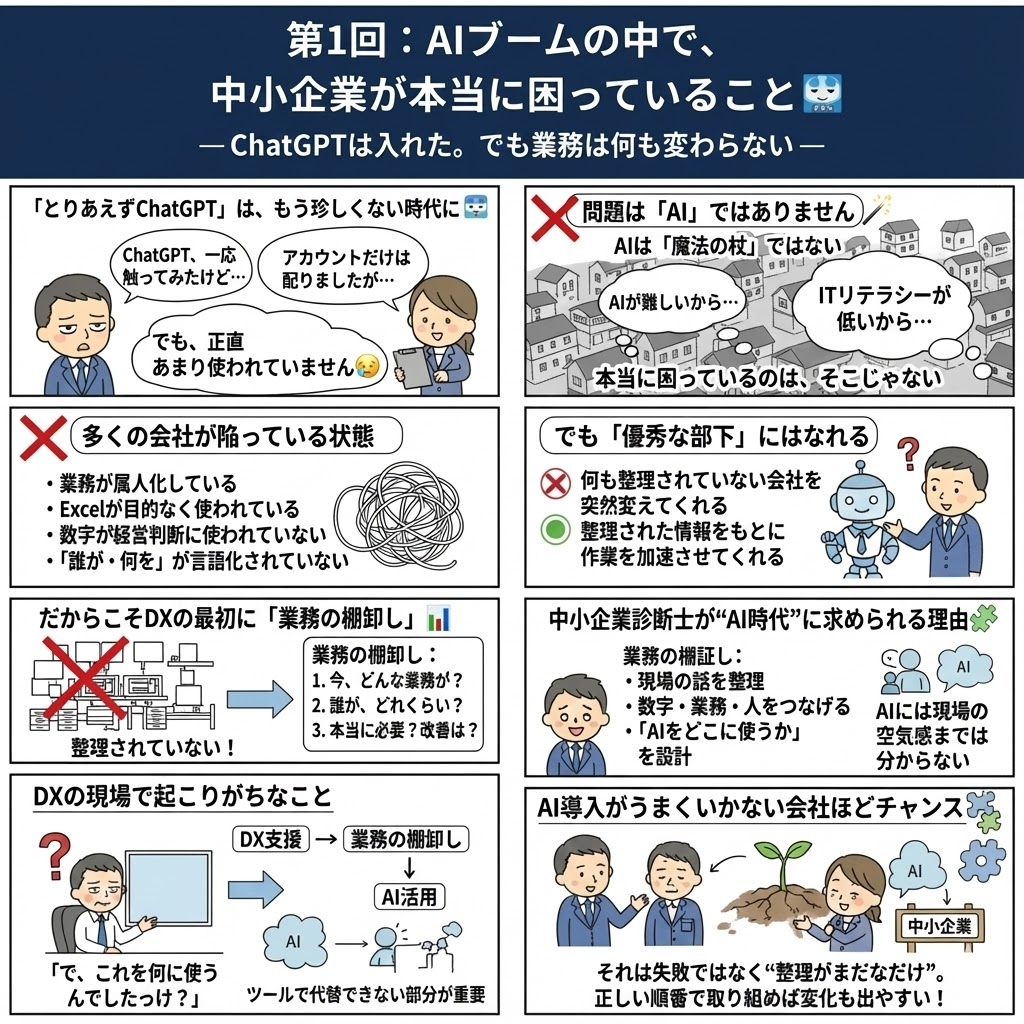2025.11.14
【Day5】成果を数値化!AI導入の効果測定と次のステップ〜“使って終わり”にしないための検証と改善〜
朝の投稿でも昼の投稿でもこんばんは。
i-consulting office(アイ・コンサルティング・オフィス)の田中健太郎です。
私は「社長も社員も、働くことが楽しいと思える会社づくり」
をお手伝いすることを使命に、中小企業の経営支援を行っています。
そんな私の提供できるサービスを考えてこんな経営者に出会いたいと考えています。
- DX推進/生成AI活用を社内に取り入れたいが何から始めていいかわからない。
- 経営数字を使った根拠ある経営判断をしたい。
- 自社の強みを見直し、根拠のある経営計画を作成したい。
- 採用・定着を実現するための理念策定・浸透を行いたい。
といろいろ書いてますが、経営に関するお困りごとは気軽にご相談ください。
当社は「わかりやすく、具体的に」をモットーに、経営の現場ですぐに役立つ支援を心がけています!
本日は「【Day5】成果を数値化!AI導入の効果測定と次のステップ〜“使って終わり”にしないための検証と改善〜〜」というタイトルで書いておきます。
導入したら、効果を見よう!前職でもシステム導入までは一生懸命やっているけれどいざ、導入が済めばそれで終わり。実際にどれぐらいの効果があったのかの検証はほとんどやっていませんでした。
これがシステム会社の悲しいところ、買ってもらうまでが仕事でその後のフォローはトラブルのみ、どんな成果が出たのかまでやっている会社はないと思います。
ちなみに、私が中小企業診断士になった理由の一つが毎月1回問い合わせするかどうかなのに高いサポート料払ってもらうぐらいなら、定期的に訪問して経営状況を確認して次の一手を提案して実行をサポートするほうにお金を払ってもらうほうがいいんじゃない?という想いがあったりします。
🌟こんな方におすすめ
- 「生成AIを導入してみたけれど、効果が実感できない」と感じている方
- AI活用の成果を経営層や他部署に、数字でわかりやすく説明したい方
- 次のステップ(社内展開・有料ツール導入・システム連携)を検討している方
🧭はじめに:AI導入のゴールは「使うこと」ではない
この5日間で、生成AI導入のステップとして
1️⃣ 意義を理解し(Whyを共有)
2️⃣ 業務を見える化し(どこで使うか整理)
3️⃣ 無料ツールで小さく試し(リスクを抑えて検証)
4️⃣ チームで共有・定着させる仕組みをつくる
…というところまで進めてきました。
しかし、本当のスタートはここからです。
「AIを使った結果、何がどれだけ良くなったのか」を数字とストーリーで説明できる状態になって、初めて「経営の道具」としてのAI導入が完成します。
生成AIは、一度入れたら終わりのシステムではなく、
“改善サイクルを回しながら育てていくツール” です。
そのために欠かせないのが、今回のテーマである「効果測定」と「次の一手」です。
📊ステップ①:AI導入の“成果指標(KPI)”を決める
AIの効果は「なんとなく便利になった」だけでは社内に伝わりません。
まずは、誰が見てもわかる指標(KPI) を決めましょう。
代表的な3つの観点は次の通りです。
| 観点 | 指標例 | 計測方法(例) |
|---|---|---|
| 時間削減 | 作業時間の短縮(例:議事録作成 60分 → 10分) | 導入前後のストップウォッチ計測・作業ログ・担当者ヒアリング |
| コスト削減 | 外注費・残業代・人件費の削減 | 経費データ・残業時間の比較 |
| 品質向上 | ミス・修正回数の減少、問い合わせ件数の減少 | 品質チェック表・クレーム件数・顧客アンケート |
ポイント
- いきなり全部を測ろうとせず、
👉 「時間削減」と「コスト削減」だけに絞る ところから始めてもOK - 測定は「導入前」と「導入後」で比較できるように、
👉 最低1〜2週間分の“導入前の実績” を残しておくと確実
例:議事録作成時間 60分 → 10分
削減時間は 50分で、削減率は約83%(50 ÷ 60 ≒ 0.83)
こうした具体的な数字があるだけで、
「現場の感覚」から「経営に伝わる資料」に一気にレベルアップします。
🧮ステップ②:成果を「見える化」するExcelテンプレートを作る
AI活用の効果を報告するには、Excelで“効果測定シート”を用意しておくのが実務的に便利です。
📘効果測定シートの項目例
| No | 業務名 | 導入前時間 | 導入後時間 | 削減時間 | 削減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 議事録作成 | 60分 | 10分 | 50分 | 83% | 月○回実施 |
| 2 | メール文作成 | 20分 | 5分 | 15分 | 75% | 定型文作成にAI活用 |
| 3 | 社内報の原稿案 | 240分 | 60分 | 180分 | 75% | 構成案と見出し生成に活用 |
※「月間削減コスト」のような金額換算を入れる場合は、
1時間あたりの人件費・実施回数などの前提を社内で統一しておくと、後から議論しやすくなります。
シート作成時のチェックポイント
- 業務ごとに行を分ける(議事録・メール・企画書など)
- 集計行を作り、月・四半期・年間の合計削減時間を集計
- 可能であれば、グラフ(棒グラフ・円グラフ)で可視化すると、経営会議での説明が一気にスムーズになります。
👉 このシートを四半期ごとに更新すれば、
「AI活用の成果レポート」としてそのまま経営会議や部門会議で使えます。
💬ステップ③:「数値+ストーリー」で社内に発信する
数字は強力な武器ですが、それだけだと「ふーん」で終わってしまうこともあります。
そこで重要なのが、“誰がどう変わったのか”というストーリーです。
例:総務部でのAI活用ストーリー
総務部の田中さんは、毎月の社内報の原稿作成にChatGPTを活用し始めました。
これまで構成案づくりから本文執筆まで約4時間かかっていた作業が、
AIに「構成案」や「見出し案」を出してもらうことで約1時間に短縮。
浮いた3時間で、新しい福利厚生企画のリサーチやアンケート設計に時間を使えるようになり、
社内アンケートでも「社内報が読みやすくなった」「企画がわかりやすい」といった声が増えました。
このように、
- 誰が(人物)
- どんな業務で(シーン)
- 何が変わり(数字)
- 結果としてどんな良いことが起きたか(効果)
をセットで伝えることで、AI活用が現場の創造性向上にもつながっていることを、周囲に実感してもらいやすくなります。
発信の場も決めておく
- 部門ミーティングで月1回「AI活用共有タイム」を5〜10分確保
- 社内ポータル・チャットツール(Teams、Chatworkなど)に「AI活用チャンネル」を作る
- 成功事例だけでなく、うまくいかなかった失敗例も共有して、ナレッジに変える
🧰ステップ④:改善サイクル「PDCA」でAI活用を進化させる
AI導入を“単発の取り組み”で終わらせないためには、
**PDCA(計画 → 実行 → 評価 → 改善)**を意識して運用することが重要です。
| フェーズ | 目的 | 具体的アクション例 |
|---|---|---|
| Plan(計画) | どの業務にAIを導入するか決める | 業務を洗い出し、「時間がかかる」「パターンが多い」ものを優先 |
| Do(実行) | 実際にAIを使ってみる | ChatGPT・Copilotでプロンプトを試行し、ひな形を作る |
| Check(評価) | 成果を測定・共有する | 削減時間・削減率・担当者の感想を効果測定シートに記録 |
| Act(改善) | 改良・展開・教育につなげる | 成功したやり方をマニュアル化し、他部署にも横展開 |
実務上のおすすめは、「3か月単位」でPDCAを回すこと。
- 1か月目:試す(トライアル)
- 2か月目:測る(効果測定)
- 3か月目:広げる・直す(横展開・改善)
というリズムを意識すると、
無理なく継続しながら「AI活用レベル」を少しずつ引き上げていけます。
🧠ステップ⑤:次のステップは“AI×業務システム”へ
ChatGPT や Copilot などのツール単体で効果が見え始めたら、
次のステップとして「既存の業務システムやツールとの連携」を検討できます。
分野別:次のステップの具体例
| 分野 | 次のステップ例 |
|---|---|
| 事務処理 | ChatGPT+Excelで、請求書・見積書・報告書のひな形を自動生成 |
| 顧客対応 | ChatGPT+LINE公式アカウント/Webフォームで、よくある質問への自動返信案を作成 |
| 社内共有 | ChatGPT+Teams/Slackで、会議録・チャットの要約を自動生成 |
| 経営分析 | ChatGPT+BIツール(Power BI など)で、売上・利益・原価のレポート説明文を自動作成 |
いきなり大がかりな開発に踏み切る必要はありません。
- まずは「人がコピペでつないでいるところ」を洗い出す
- 次に、「ここが自動化できたら楽になる」というポイントを特定する
- 必要に応じて、SaaSやRPA、API連携などを検討する
という流れで、少しずつ“業務インフラ”としての生成AI活用に近づけていくイメージです。
📈導入効果を“経営指標”に変える方法(ROIの考え方)
AI活用を経営レベルで判断してもらうには、
「時間削減」などの効果を“お金”に換算することが有効です。
💡シンプルな計算例
- 1時間あたりの人件費(給与+社会保険料等を含む社内試算)を 2,500円 と仮定
- 年間で 300時間 の削減ができた場合
2,500円 × 300時間 = 年間75万円 の生産性向上効果
もちろん、これはあくまでモデル計算なので、
実際には自社の人件費や稼働状況に合わせて前提条件を決める必要があります。
それでも、
- AIツールやコンサル費用などの投資額
- 時間削減・コスト削減を換算した効果額
を並べて示すことで、AI投資の妥当性(ROI)を経営層に説明しやすくなります。
🚀次のステップ:AI活用を「仕組み化」する
AI導入が一通り回り始めたら、
次のフェーズは「属人的な取り組み」から「会社の仕組み」に昇華させることです。
1️⃣ AI活用マニュアルの作成
- 各部署での具体的な活用例(プロンプト例・手順)
- 情報漏えいを防ぐための禁止事項・注意事項
- 推奨するツールや設定(アカウント管理・ログの扱い など)
を1つのドキュメントにまとめておくと、
新しく参加するメンバーも同じルールでAIを活用できます。
2️⃣ 社内AI研修の実施
- 新入社員向け: 基本操作・リスク・社内ルール
- 管理職向け: 業務改善・KPI設定・評価の仕方
といったように、対象者ごとに研修内容を分けると効果的です。
「AIで何ができるか」だけでなく、
「部下にどう使わせ、どう評価するか」まで伝えられると、組織として前に進みやすくなります。
3️⃣ 経営戦略への組み込み
- 中期経営計画や年度計画の中に、
「AI活用KPI」や「AI活用による生産性向上目標」を明記する - 「AI推進担当」や「AI推進チーム」を正式な役割として位置づける
ことで、AI活用が一部の熱心な人の活動ではなく、
会社としての取り組みとして定着していきます。
🧭まとめ:AI導入は「改善の連続」で価値を生む
生成AIの導入は、ゴールではなくスタートラインです。
- 導入する
- 活用してみる
- 効果を測る
- 改善し、広げる
というサイクルを回し続けることで、
中小企業でも十分に生産性と創造性を高めていくことが可能です。
最後にもう一度、このシリーズで紹介した5つのステップを振り返ります👇
1️⃣ 意義を理解する(Day1)
2️⃣ 課題・業務を見える化する(Day2)
3️⃣ 無料ツールで小さく試す(Day3)
4️⃣ チームで共有・定着させる(Day4)
5️⃣ 成果を数値化し、改善と次のステップにつなげる(Day5)
これらを愚直に回していけば、
規模の小さな企業でも**自社なりの「AI導入成功パターン」**を必ず作ることができます。
💬最後に:AI導入は“完璧”よりも“継続”
最初から完璧なKPI設計や、完璧なプロンプトを目指す必要はありません。
大切なのは、
試す → 学ぶ → 少し改善する
という小さな一歩を、止めずに積み重ねていくことです。
AIは、継続して向き合う企業・チームにこそ、
時間・お金・アイデアという大きなリターンを返してくれます。
ぜひ明日からも、
「1日1業務、AIで少し楽にしてみる」
を合言葉に、
生成AIを味方につけた“新しい働き方”に踏み出していきましょう。
これで
「5日でわかる!中小企業のための生成AI導入ステップガイド」シリーズは完結です🎉
次のテーマでも、実務で使える生成AI・DXのノウハウをお届けしていきます。
お問い合わせ
本日は「【Day5】成果を数値化!AI導入の効果測定と次のステップ〜“使って終わり”にしないための検証と改善〜」というテーマのブログを書かせていただきました。中小企業様の生成AI導入の参考になれば幸いです。
i-consulting officeでは生成AI導入のための研修・導入支援を行っています。
ご興味・ご関心のある方はぜひお問い合わせください。
お問い合わせページ:https://icon-office.com/contact
Instagram:https://www.instagram.com/i_consulting_offic👈Instaフォローお願いします!
LINE公式アカウント:https://lin.ee/xHeD62c
宜しくお願いします!
本日のお仕事
今日も就労支援関連のコンサルティングのお仕事です。
・あとはDXセミナー資料作成 相変わらず進まない
・本当はやっておきたい就労支援施設に導入されている機械の使い方のレクチャー事前予習
・AI導入支援のための事前調査依頼事項への対応
この辺が金、土、日でできるのだろうか?急に寒気がしたので我ながら体調管理も問題。